地震大国の日本では近年も全国各地で大きな地震に襲われています。「わが家の耐震性は大丈夫かな?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。耐震性を向上させるリフォームする場合、補助金制度があることをご存知でしょうか。今回の記事では、耐震リフォームの補助金制度と、補助金を利用する前に知っておきたい知識や耐震診断について、わかりやすく解説します。
「耐震リフォーム」をすべきか、どう判断する?

「旧耐震基準」「新耐震基準」を確認する
耐震リフォームを考える際、目安となるのが「耐震基準」です。「耐震基準」とは、建築物がどれだけ地震に耐えることのできる構造かを判断する基準となります。耐震基準は「旧耐震基準」と「新耐震基準」に分かれ、「建築確認申請」が受理され「確認通知書(副)」が発行された日付で確認することができます。
【旧耐震基準】1981年(昭和56年)5月31日以前
【新耐震基準】1981年(昭和56年)6月1日以降
「旧耐震基準」は、震度5強程度の揺れでも建築物が倒壊せず、破損した場合でも補修することで生活が可能であることを想定した基準です。一方で「新耐震新基準」は、震度5強程度の地震ではほとんど損傷せず、震度6強から震度7程度の揺れでも倒壊しないことを目標にした基準です。お住まいの家が1981年5月以前に建てられた「旧耐震基準」に該当していれば、耐震リフォームを検討する目安となります。
木造住宅は「2000年基準」にも注意
耐震基準には、「旧耐震基準」「新耐震基準」のほかに「2000年基準」もあります。これは、2000年(平成12年)6月に建築基準法が改正され、木造住宅に関する耐震基準の変更が行われたものです。震度6強から7程度の揺れでも倒壊しないという基準は変わらず、さらに、地盤に応じた基礎設計や、柱頭・柱脚・筋交いの接合方法、偏りのない耐震壁の設置などが定められて、「新耐震基準」をより強化した基準と言えます。「新耐震基準」に適合する木造住宅でも、2000年6月からの改正基準に適合していない場合は、注意が必要です。
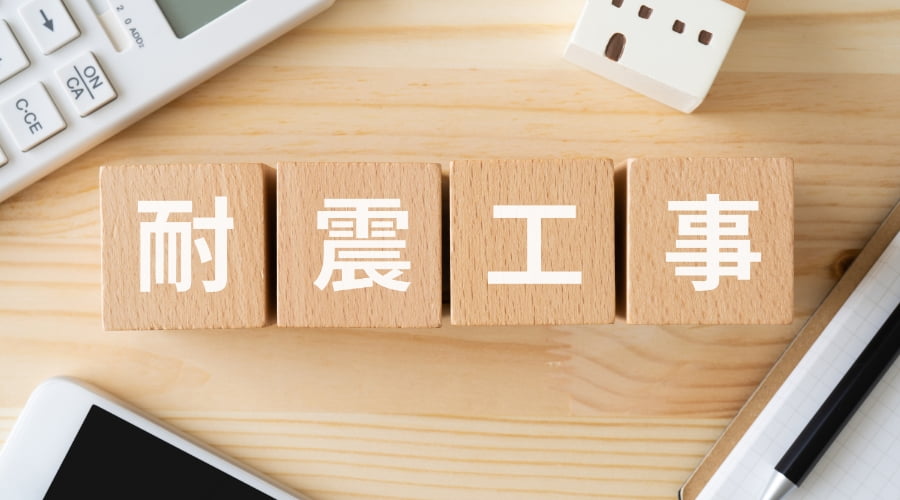
耐震リフォームの補助金制度とは?

補助金は自治体から支給され、「耐震改修」と「耐震診断」の2種類ある。
多くの自治体では、建物の倒壊など地震による被害を最小限に抑えるために、「耐震診断」や「耐震リフォーム」に関する補助金制度を実施しています。どの自治体も基本的には、工事契約と着工前に「耐震診断」を受けることが支給条件の一つとなっています。ただし、補助金の対象となる住宅や工事などに関する細かな条件や、工事費用に対する補助率や補助金の限度額などは、自治体ごとに異なります。補助金制度を実施していない自治体もあり、補助金の募集期限を設定しているところもあります。正確な情報は、居住する自治体のホームページなどでチェックしましょう。
「耐震診断」とは?
「耐震診断」とは、既存建築物の耐震性能を評価し、耐震リフォームが必要かどうかを判断するものです。「耐震診断」の大まかな流れは、「予備調査」「現地調査」「耐震診断結果の評価」の3つの順で行われます。「予備調査」は、現地調査(本調査)を行う際に診断方法を決定するための調査です。「現地調査」は、現地で構造躯体や非構造部材、設備機器などの状況を確認し、強度や劣化の状況などの詳細を調査します。これらの調査が終了した後に、「耐震診断結果の評価」が行われます。

補助金制度の調べ方は?

耐震リフォームの補助金対象となるおもな条件
耐震リフォームの補助金対象となる住まいには、いくつかの条件があります。この条件は主に住宅の「築年数」「構造」「建物の用途」によって決められています。「築年数」については「旧耐震基準」で建てられた木造住宅が対象となるケースが多く、1981年年5月31日以前に建てられた住宅が該当します。「構造」については木造軸組み工法で建てられた2階建て以下の住宅が対象となります。「建物の用途」に関しては、居住を目的とした戸建て住宅が対象となり、賃貸住宅などで所有者と居住者が異なる場合は、所有者が耐震診断を受けることが条件となります。
自治体が実施する補助金を確認する方法
自治体の補助金制度を確認する際は、居住するエリアの市役所・区役所のWEBサイトや、窓口で確認しましょう。一般社団法人住宅リフォーム推進協議会が運営する「住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」も便利です。「耐震リフォーム」の補助金制度だけでなく、省エネルギー化やバリアフリー化など、各自治体が提供するさまざまなリフォームに関する補助金制度を検索できます。また、「耐震リフォーム」に対応するリフォーム会社に相談してみるのもよいでしょう。
「減税措置」も適用できるの?

耐震リフォームに対する減税措置
耐震リフォームには減税措置も適用されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
・所得税の特別控除
所得税の特別控除は、「リフォーム促進税制」と「住宅ローン減税」があります。住宅ローンを利用している場合は、この2つを併用することも可能です。返済期間が10年以上ある住宅ローンを組んで耐震リフォームを行う場合、「リフォーム促進税制」と「住宅ローン減税」の2つに申請することができます。
・固定資産税の減税
「耐震リフォーム」を行った場合、「固定資産税」も減税されます。「固定資産税」の減税は1982年1月1日以前からある住宅を対象に、耐震リフォーム費用が50万円(税込)を越えた場合に適用され、1年間、家屋の固定資産税額の2分の1が減税となります。固定資産税の減税措置を受けるには、耐震リフォームが完了してから3ヶ月以内に各自治体へ申告する必要があります。独自の固定資産税の減税制度を設けている自治体もあるので、確認することをおすすめします。
・その他の減税措置
「耐震リフォーム」は、親や親族から住宅取得等資金を贈与により受けた場合、贈与税が一定金額まで非課税になる減税措置があります。また、耐震リフォームなど改修工事を行った中古住宅を購入して居住する場合、登録免許税の税率が0.3%軽減されます。改修工事を行った中古住宅を譲渡した際には、宅地建物取引業者に課される不動産取得税が減額されるケースもあります。
まとめ
地震の多い日本では、住まいの耐震性を無視することはできません。住んでいる家の「耐震リフォーム」が必要かどうかの目安として、「耐震基準」があります。「旧耐震基準」の住まいの場合、耐震リフォームを検討してみましょう。その際、まずは「耐震診断」を受けて判定してもらいましょう。耐震リフォームを行う際は、自治体の補助金制度や減税措置を利用して費用を抑え、安心できる住まいを実現してください。


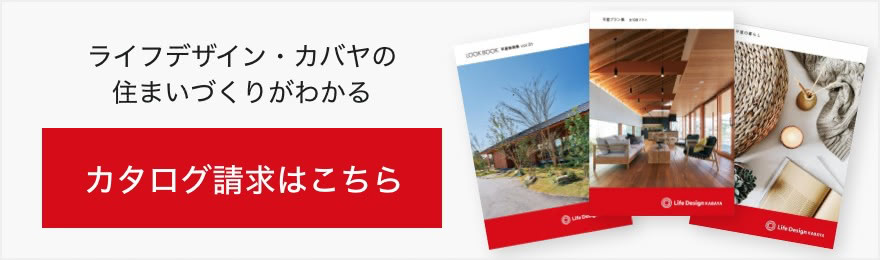
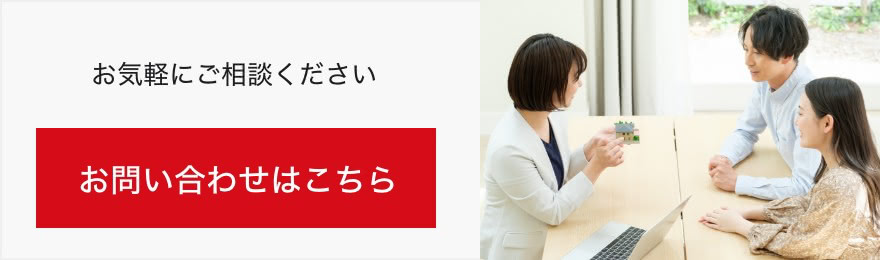
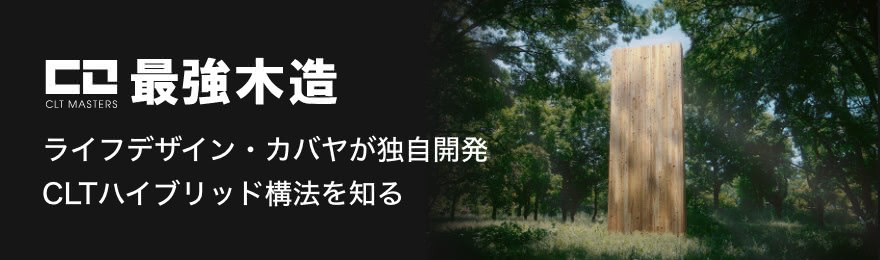




 モデルハウス
モデルハウス イベント情報
イベント情報 カタログ請求
カタログ請求